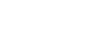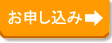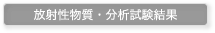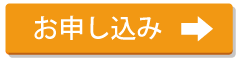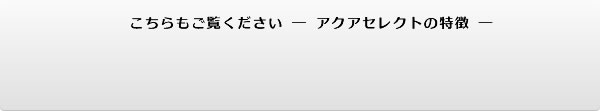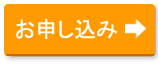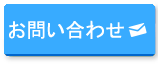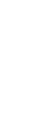水のはなし
天然水の人びと
アクアセレクトGMの竹本大輔による水紀行
第38回 浦村奇跡の牡蠣編3
間近に見る「絣(かすり)模様」と言われる牡蠣の養殖筏(いかだ)。津波が押し寄せてくると、ひとたまりも無いのだという。

牡蠣養殖の歴史、自然災害
竹本
さきほど、昭和40年代前半に真珠があまり良くなくって、そこから養殖牡蠣が広まったと聞きました。このあたりの歴史についてお話しいただけますでしょうか?
村田理事
歴史的には昭和2年くらいから、ぼちぼちと他の地域に住む人がやってこられて始められたんです。そいで昭和10年頃には、地元の人も参入したみたいですね。
竹本
なるほど。
村田理事
ほいで、転機となったのは、昭和35年にチリ津波があったときなんです。岩手県でも何百人もの方が亡くなられました。
この浦村では、そのときにだいたい、真珠筏(いかだ)が半分、牡蠣筏が半分、1200台くらいの筏のうち半分半分がダメになりました。その後40年代になってから真珠の不況で、殆どの筏が牡蠣に変ってしまった、という歴史があります。
この浦村では、そのときにだいたい、真珠筏(いかだ)が半分、牡蠣筏が半分、1200台くらいの筏のうち半分半分がダメになりました。その後40年代になってから真珠の不況で、殆どの筏が牡蠣に変ってしまった、という歴史があります。
竹本
チリ津波が契機になって?もしくは不況の影響なんでしょうか?
村田理事
一番は不況でしょうな。チリ津波の影響があって、その翌年に伊勢湾台風が来たんです。つまり2年連続で自然災害に襲われたことになります。
竹本
翌年だったんですか…。
山本支所長
チリ津波の時、ものすごく「裂けた」んですよ。
竹本
「裂けた」とはどういうことでしょうか?
山本支所長
潮が引いて海が裂けたんですわ。この堤防の所まで裂けとんやってに。
村田理事
この間の東日本も津波結構きつかったけどね。
山本支所長
真珠筏もわやになった(ダメになった、使い物にならない様子)。牡蠣筏もみんなわややったね。
竹本
潮の力ですね。潮の満ち引きで筏がぐちゃぐちゃっとなるんですね。
山本支所長
満ち引きの力でそうなるんですな。アンカー打ってあるんやけど、潮が満ち引きする力の前ではもうアンカーなんか何の意味もないんさ。アンカーがねじれて切れとんやんな。この前の震災でも60キロ以上のアンカーが6丁うってあるんやけどな、それがねじ切れて、船が通っていくように、すーっと引っ張っていくんさ。波の高さで言うと2~3メートルくらいかな?ちなみにチリ津波の時は5~6メートル動いたな。
山本支所長
この前の筏が、窓から見えなくなるくらい引くんです。
村田理事
今回の東日本大震災の津波は、どっちか言うと、外へ流れ出さんと奥へいったんやな。
この島との間で丁度狭くなっているということと、丁度湾口が北東向きになっとるのが原因でしょうな。
この島との間で丁度狭くなっているということと、丁度湾口が北東向きになっとるのが原因でしょうな。
山本支所長
だから太平洋の波を受けるのに丁度良いような湾口の形になっとるんやけど、湾口の奥の部分へ行けば行くほど狭くなっとるから、津波が来たらこの辺は一発でアカンやろうな。
竹本
津波に対する対策なんかされてるとは思うんですが、どうういった対策なんでしょうか?
村田理事
地形は三陸海岸とよく似とるんです。ただ海岸から急激に標高があるんで、津波からは逃げやすいんさ。
竹本
すっと高くなってますもんね。なるほど。
村田理事
昔から津波はすごい多いと聞いとるんです。ただむかしからの津波の歴史を見とると、安政の東海沖地震でも死者はゼロなんです。あ、例外的に一名おったけどな。例外的に一名、歩けえへん子供が置いとかれて津波に流されたんです。お母さん働きにどこか山の中に入っとって。一般的に動ける人は誰も死んでない。
竹本
なるほど、高齢化なんかで心配なところではありますけれど、そういった地の利があるということですね。
村田理事
まあ財産とか確かにこういう営業施設なんかは、津波くると大変なんやけど、人命的にはあまり心配してないんですよ。
竹本
それは何よりだと思います。ただこういった複雑な海岸線を持つ地域はやっぱり津波との戦いなんですね。
後世に伝えていかなければならない貴重なお話を伺えた。

穏やかな海。守っていきたい日本の風景。

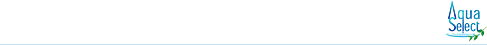
竹本大輔