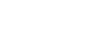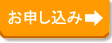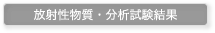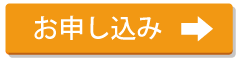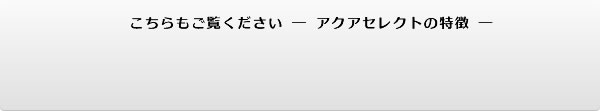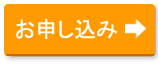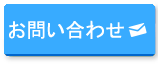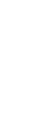水のはなし
天然水の人びと
アクアセレクトGMの竹本大輔による水紀行
第50回 妙高上越 食の魅力 武蔵野酒造さま編4
日本の酒、から世界の日本酒へ
新潟県上越市の「株式会社武蔵野酒造」の玄関に置かれた誇らしげな酒とその受賞履歴を表す数々の賞状やトロフィー。
この歴史ある酒蔵が出す酒の名も「スキー政宗」や「春日山天と地」と洒落ている。
この歴史ある酒蔵が出す酒の名も「スキー政宗」や「春日山天と地」と洒落ている。

今回はその中でも「スキー正宗 入魂」の話題から。

竹本
ついつい、スキーそのものの話に脱線してしまいました(笑)
「スキー正宗」の話題に戻りたいと思います。
「スキー正宗 入魂」という銘柄についてもホームページで拝見致しました。
「1級酒や特級酒で売っても良いお酒をあえて2級酒として発売したのがこの『スキー正宗 入魂』。 灘や伏見の大手蔵に対抗する一つの手段だった」とありました。
このあたりのお話をお伺いできますか?
「スキー正宗」の話題に戻りたいと思います。
「スキー正宗 入魂」という銘柄についてもホームページで拝見致しました。
「1級酒や特級酒で売っても良いお酒をあえて2級酒として発売したのがこの『スキー正宗 入魂』。 灘や伏見の大手蔵に対抗する一つの手段だった」とありました。
このあたりのお話をお伺いできますか?
小林社長
1992年まで酒造法に日本酒の等級制度というのがあったんですね。特級、一級、二級とあって、これを国税庁に申請して認定されるという制度なんです。ただ味ではなく、あくまでも税率で分けていた制度なんです。で、基本的には税務署で、これは、一級だね、これは特級だねっていう審査を受けるんです。でも審査を受けなければ全部無級なんです。で、税金、コスト的な差が値段に出てくる訳です。級別で値段が違うということになるんですね。
でここから本題なんですが、新潟県の地酒ブームの一つは「低価格で美味しいお酒が多いね」ってとこだったんです。
それが全部「二級酒」だった。ただ当時は、特に関西方面では絶対に特級酒や一級酒しか飲まなかった時代なんです。「でも新潟県のお酒二級でも美味しいね」って、少しマニア的な人達が騒ぎ初めた。
中でも「越乃寒梅」さんって有名銘柄もそういった機関車的役割を果たして、新潟のお酒地酒って美味しいよっていう雰囲気がここ30年ぐらい前に盛り上がったんですよね。
でここから本題なんですが、新潟県の地酒ブームの一つは「低価格で美味しいお酒が多いね」ってとこだったんです。
それが全部「二級酒」だった。ただ当時は、特に関西方面では絶対に特級酒や一級酒しか飲まなかった時代なんです。「でも新潟県のお酒二級でも美味しいね」って、少しマニア的な人達が騒ぎ初めた。
中でも「越乃寒梅」さんって有名銘柄もそういった機関車的役割を果たして、新潟のお酒地酒って美味しいよっていう雰囲気がここ30年ぐらい前に盛り上がったんですよね。
竹本
ははぁ。
小林社長
そこから新潟県の地酒ブームっていうのがあるわけなんですよ。
われわれの「スキー正宗 入魂」っていうのは、値段は二級並みなんだけど、特級・一級クラスの酒質だっていうふうな訴えかけで世に出したものなんです。ただ数量のこともあるし、「登録店」という制度で、販売店の方に限定させていただきました。
われわれの「スキー正宗 入魂」っていうのは、値段は二級並みなんだけど、特級・一級クラスの酒質だっていうふうな訴えかけで世に出したものなんです。ただ数量のこともあるし、「登録店」という制度で、販売店の方に限定させていただきました。
竹本
へー、そういう等級酒の流れの中で生まれたお酒なんですね。
小林社長
それで販売しているお酒。だから原価がかかりすぎちゃって商売的には、あまり儲からないんです。値段が安いしね(笑)
竹本
でも、それはブームになりそうですね。
「新潟のお酒は二級のお酒でも品質がイイよ、美味しいよ」っていうのが今でも続いているんですか?
「新潟のお酒は二級のお酒でも品質がイイよ、美味しいよ」っていうのが今でも続いているんですか?
小林社長
ブームとしてはまず関西だったんですが、東京もそれに続いて起こりましたね。
ただ今はどっちかって言うと、級別もなくなりましたから、例えば純米であるとか、純米吟醸であるとか、それを総称して「特定名称種」って言うんですけど、それらがウケてる。今は出荷のほとんどが特定名称種になってきますね。高品質のいわゆる「純米吟醸」とか「純米」とか「大吟醸」っていうカテゴリーになってきています。東京でウケているのは「高品質のお酒」ということでしょうね。
ただ今はどっちかって言うと、級別もなくなりましたから、例えば純米であるとか、純米吟醸であるとか、それを総称して「特定名称種」って言うんですけど、それらがウケてる。今は出荷のほとんどが特定名称種になってきますね。高品質のいわゆる「純米吟醸」とか「純米」とか「大吟醸」っていうカテゴリーになってきています。東京でウケているのは「高品質のお酒」ということでしょうね。
竹本
なるほど。なるほど。「高品質」ですね。
先ほどブームって言うお話がありましたけど、最近また「日本酒ブーム」というように言われていますが、小林社長はどうお感じですか?
先ほどブームって言うお話がありましたけど、最近また「日本酒ブーム」というように言われていますが、小林社長はどうお感じですか?
小林社長
まだまだだなあ(笑)
竹本
そうですか。まだまだですか。
ちょっと世間が騒いでる感じがするんですが?
ちょっと世間が騒いでる感じがするんですが?
小林社長
ちょっと「和食」自体が無形文化遺産に登録されて、「合わせて日本酒も」という流れは、できつつある気はしますけど、まだ「ブーム」って言うほどでもないですね。
※(編集部注)2013年12月、「和食;日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。
※(編集部注)2013年12月、「和食;日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。
竹本
今後の展望としてはいかがですか?
小林社長
日本酒業界的、数値的にはずっと右肩下がりです。ただ下がる幅は少し止まってはきてますけどね。背景的には人口の減少だったり、いわゆる少子化だったりという部分でいうと、あんまり需要増加に繋がるとは思えません。
ただ、伸びていく要素があるんだとすれば「輸出」です。これまでの「日本の酒」から「世界の日本酒」みたいな、育ち方をすると、面白いなとは思います。逆の言い方をすると、もうそれしかない、って感じますね。
ただ、伸びていく要素があるんだとすれば「輸出」です。これまでの「日本の酒」から「世界の日本酒」みたいな、育ち方をすると、面白いなとは思います。逆の言い方をすると、もうそれしかない、って感じますね。
竹本
こちらでは、どれくらい輸出とかで出されているんですか?
小林社長
いやいや、まだまだ国内がメインです。5%とかそんなもんです。
竹本
なるほど。これからは増やしていこうと?
小林社長
そうですね。
竹本
主にどのあたりの地域が多いのですか?
小林社長
アメリカが多いですよね。
竹本
理由はなんなんでしょうか?
小林社長
やはり人口が多いってのが一つあります。人口が多いということは市場としてとても魅力です。
それに何より言えることは、アメリカはやっぱり食文化が成熟しているということが言えると思います。
日本酒が分かる方が多い。扱う方も日本酒を勉強されてる方が多いんです。
良い酒と悪い酒の見極めはきちんとしていかなければダメだ、というふうなところもある。
いわゆるワインで慣れてるんですね。カテゴリー的には醸造酒で日本酒もワインも同じです。
ですからワインのソムリエさんなんかも、きちんと日本酒ていうのも評価もしてくれたりするわけですよね。
ぼくらにとって「品質をきちんと分かってくださる人」がどれだけいるかということがとても重要だと思うんですね。
そう考えるとやっぱりアメリカが、消費者そしてプロフェッショナルすべて含めていらっしゃることが強みなんだと思います。
それに何より言えることは、アメリカはやっぱり食文化が成熟しているということが言えると思います。
日本酒が分かる方が多い。扱う方も日本酒を勉強されてる方が多いんです。
良い酒と悪い酒の見極めはきちんとしていかなければダメだ、というふうなところもある。
いわゆるワインで慣れてるんですね。カテゴリー的には醸造酒で日本酒もワインも同じです。
ですからワインのソムリエさんなんかも、きちんと日本酒ていうのも評価もしてくれたりするわけですよね。
ぼくらにとって「品質をきちんと分かってくださる人」がどれだけいるかということがとても重要だと思うんですね。
そう考えるとやっぱりアメリカが、消費者そしてプロフェッショナルすべて含めていらっしゃることが強みなんだと思います。
竹本
なるほど。
そう考えると、食文化の成熟度っていうのは結構大きなファクターですね。
そう考えると、食文化の成熟度っていうのは結構大きなファクターですね。
小林社長
そうです。やっぱりアメリカなんかはきちっとした物をお出しすれば良さをわかってくれるし日本の文化的な部分まできちっと理解してくれるんで、いわゆる「日本食レストラン」でお酒を飲むオーダー率は高いですよ。
竹本
日本人よりそういう意識が高いかもしれませんね。
小林社長
そうですね。
竹本
「日本酒のソムリエ」みたいな職業があるんですよね?
小林社長
ありますね。まだ世界ではメジャーとは言えませんが、増えていますね、ヨーロッパあたりとかで。
日本でも東京で増えたりして、その人たちがここ新潟にお客様をお連れするツアーなんかも出てきています。
日本でも東京で増えたりして、その人たちがここ新潟にお客様をお連れするツアーなんかも出てきています。
竹本
実は、大台町に唯一ある酒蔵を取材させていただいた時に「もう『お燗番』って言葉が廃れてますよね」という話になったので、嬉しい話題ですね。
小林社長
そうですね。
「スキー正宗 入魂」から日本酒の等級制度、そして輸出、ソムリエ、食文化の成熟について。
本当に小林社長の話題は、幅が広く、そして深い。
本当に小林社長の話題は、幅が広く、そして深い。

厳しいご意見の中にも柔和な笑顔を見せられる。何時間も話し込んでしまった。