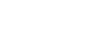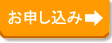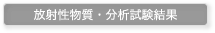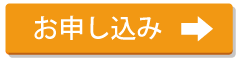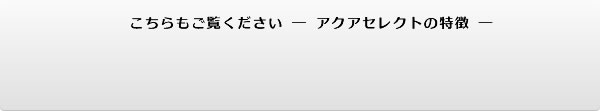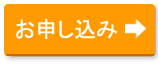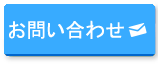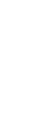水のはなし
天然水の人びと
アクアセレクトGMの竹本大輔による水紀行
第47回 妙高上越 食の魅力 武蔵野酒造さま編1
天然水の人びと連載も、早1年。
これまでアクアセレクトの採水地である三重県多気郡大台町、そして日本一の清流「宮川」流域を中心に、取材を重ねてきた。
この取材で教えられたことは、圧倒的に豊かで素晴らしい自然環境が存在するということ。
そしてそこに生きる人たちの熱い思いだった。
まだまだ、日本国内には豊かな自然環境が残っていることを私は知っている。
であれば、その地域で愛されている「天然水」があるはず。
そして、きっとそこには天然水に関わる素敵な「人」たちもいらっしゃる、はず。
そうなると、本ページのタイトルの「天然水の人びと」の看板に偽りなし、だ。
取材を通してそんな確信を得た。
たまたま、先の震災の際にご縁を得た、天然水宅配の同業者であられる、新潟県妙高市の「須弥山合同会社」さんに、再び連絡を取った。
するとどうだろう。
彼の地でボトリングされる「須弥山の天然水」を、日本酒の仕込みに使っている酒蔵がある、というではないか。
その酒蔵「武蔵野酒造」が出す酒の名前も「スキー正宗」や「春日山天と地」と洒落ている。
仕込みに天然水をわざわざ使う酒蔵、そしてこのネーミングセンス。
何はともあれお話が聞きたいと思い、取材を申し込んだ。
酒蔵にとって一年で最も忙しい「寒の時期」。
「株式会社武蔵野酒造」の小林元(はじめ)社長に広範囲に及ぶお話をお聞かせいただいた。
これまでアクアセレクトの採水地である三重県多気郡大台町、そして日本一の清流「宮川」流域を中心に、取材を重ねてきた。
この取材で教えられたことは、圧倒的に豊かで素晴らしい自然環境が存在するということ。
そしてそこに生きる人たちの熱い思いだった。
まだまだ、日本国内には豊かな自然環境が残っていることを私は知っている。
であれば、その地域で愛されている「天然水」があるはず。
そして、きっとそこには天然水に関わる素敵な「人」たちもいらっしゃる、はず。
そうなると、本ページのタイトルの「天然水の人びと」の看板に偽りなし、だ。
取材を通してそんな確信を得た。
たまたま、先の震災の際にご縁を得た、天然水宅配の同業者であられる、新潟県妙高市の「須弥山合同会社」さんに、再び連絡を取った。
するとどうだろう。
彼の地でボトリングされる「須弥山の天然水」を、日本酒の仕込みに使っている酒蔵がある、というではないか。
その酒蔵「武蔵野酒造」が出す酒の名前も「スキー正宗」や「春日山天と地」と洒落ている。
仕込みに天然水をわざわざ使う酒蔵、そしてこのネーミングセンス。
何はともあれお話が聞きたいと思い、取材を申し込んだ。
酒蔵にとって一年で最も忙しい「寒の時期」。
「株式会社武蔵野酒造」の小林元(はじめ)社長に広範囲に及ぶお話をお聞かせいただいた。
名峰、妙高山。須弥山の異名もあるこの山、訪れたのは2月。この季節にしては非常にめずらしく、晴れ間をのぞかせその雄姿を見せてくれた。

「スキー正宗」、そして「春日山天と地」など、個性的な酒が並ぶ

素晴らしい土蔵。いまは一部貯蔵にのみ使っている。どーんと横たわる梁(はり)は、その体躯を支える十分な太さと風情を持っていた。

竹本
初めまして。今日はお忙しい中ありがとうございます。さっそくなんですがご経歴をお教えいただけますか?
小林元社長
生まれてちょっと渋谷にいたんですけども、それから小学校1年生まで松戸に住んで、小学2年生から文京区。東京生まれの東京育ちです。ここはぼくの父の実家で、ここにおじいちゃんおばあちゃんが居たんですね。
それで、夏とか冬とか遊びに来たり、特にスキーをしに来たりしました。
で、いろいろな事情で家業を継ぐようになっちゃったんですが、それが大学4年生のとき。
ぼくは旅行が好きで、旅行会社に就職したいなっと思って、色々就職活動もしていたたところ、父に帰ってこいって言われて。東京慣れてし、田舎は嫌だよって言ってたんだけど、酒造りもいいかなって思ってこちらに来ました。
それで、夏とか冬とか遊びに来たり、特にスキーをしに来たりしました。
で、いろいろな事情で家業を継ぐようになっちゃったんですが、それが大学4年生のとき。
ぼくは旅行が好きで、旅行会社に就職したいなっと思って、色々就職活動もしていたたところ、父に帰ってこいって言われて。東京慣れてし、田舎は嫌だよって言ってたんだけど、酒造りもいいかなって思ってこちらに来ました。
竹本
なるほど。笑
小林社長
ただ、大学卒業してそのまま入ると世間知らずになっちゃうからということで、大阪の商社に5年いました。
竹本
そうですか。
小林社長
その商社で5年間修行させてもらい、その後は国税庁に醸造試験場ってのがあってそこの研究機関で、半年ちょっと修行しました。でもこの上越には知り合いがいないじゃないですか。それで、寂しくて寂しくて東京のネオンも恋しいし。
竹本
そうですよね。笑
小林社長
地元でも知っているのはどうしても、親父の世代、親父の友達とかです。それで同じ世代の人たちと交流を持ちたいと思い、地元の青年会議所(JC)に入りました。で、色々活動してみて「人作り」「街作り」ということを学んで体験させてもらいました。
竹本
小林社長と牧野社長(須弥山合同会社社長)にお聞きしたいのですが、「地元の育ちでない良さ」ってなにかありますでしょうか?
牧野社長
私もこちらの地元育ちではないんです。
だからこそ、こういったこちらの良さが逆に分かるという強みがありますね。どうやったら、都会の人達をこの田舎に呼べるとかに強いんだと思います。
だからこそ、こういったこちらの良さが逆に分かるという強みがありますね。どうやったら、都会の人達をこの田舎に呼べるとかに強いんだと思います。
小林社長
それはありますね。地元の人達が「こんなん都会の人間は絶対関心ねーよ」っていう所に「いやそうじゃないんじゃないか?」と関心があったり、地元の人が自慢してることろが、逆に「そんなん自慢にならねーよ」ってなったりしますね。そういう感覚っていうのは、他所の人の方が、あるんじゃないかな?
竹本
なるほど、そうですね。
小林社長
あとね、ここ最近どこの地方でも「街のあり方が中途半端」ということも感じています。街のあり方として、例えば市長になってね、住んでる人が住みよい街であれば、それでいいよ、というのもアリだと思うんです。別に外から観光客とか呼んできて外貨をとる必要性もないよって。それはそれでひとつの「街の生き方」になってきて面白いと思うんですけどね。それを中途半端にやっていくと、全部中途半端になっちゃう。逆に鎖国をした方が人が来るかもしんない。笑
竹本
今の時代、どっちかに尖ってるほうがいいかもしれない、っていうのはありますよね。笑
小林社長
日本の田舎って似たような風景だと思うんです。町並みはいっしょだし、ロードサイドにある店はみんないっしょじゃないですか。
竹本
そうですね。
小林社長
よくぼくが言ってることなんだけど、「写真に撮るとどこの町かわかんない」ってことが多々あると思うんです。
ただ、経済的な観点から言うと、外貨を獲得していかないと、地方としては成り立たなくなるのも事実です。
経済的に成り立たなくなる、行き詰まるって話がありますが、それが20年後なのか30年後なのか、誰にも分からないんです。
で今の当事者は「そんなの先だろう」、「おらは、そんな時代いねえよ」という感覚が大半を占めているのかもしれません。
ただ、経済的な観点から言うと、外貨を獲得していかないと、地方としては成り立たなくなるのも事実です。
経済的に成り立たなくなる、行き詰まるって話がありますが、それが20年後なのか30年後なのか、誰にも分からないんです。
で今の当事者は「そんなの先だろう」、「おらは、そんな時代いねえよ」という感覚が大半を占めているのかもしれません。
竹本
ぼくらアクアセレクトの採水地の三重県多気郡大台町っていう場所も、限界集落といわれる集落を沢山抱えています。ちょうどV字渓谷に沿って集落があるんですね。そこにへばり付くような形で集落が点在している。
一部には「限界集落なんて放っておけば、そのうち消滅するんだから良いんじゃないか」というある意味極端な考え方もあるのは事実です。ただ一方で「なんとか限界集落をなくして、人を住まわせよう」という動きもあります。そういうどちらも正論を吐く中で、やることが中途半端っていうのは致命的だと思いますね。
一部には「限界集落なんて放っておけば、そのうち消滅するんだから良いんじゃないか」というある意味極端な考え方もあるのは事実です。ただ一方で「なんとか限界集落をなくして、人を住まわせよう」という動きもあります。そういうどちらも正論を吐く中で、やることが中途半端っていうのは致命的だと思いますね。
小林社長
実際のところ、地元だけの取り組みでは、やっていけないんですよ。この新潟県上越市の周りにも限界集落はいっぱいあります。その限界集落を支えてやっていくのは、やっぱり里の人達なんです。できればそれは同じエリアの中が望ましいと思っています。いわゆる限界集落の端っこの人達だけで「なにかやろう」っていっても無理な話なんです
竹本
同じエリアで支え合うっていうのは、その通りですね。
小林社長
若者は限界集落から里の方へ出てきているんです。家を里の方へ建てて、勤めもこっちだし、もう限界集落の方には住まなくなってる。上越市もトータル的に人口は減ってないんですけれど、よく見ると山の人達が里に降りて来ている現状があります。
牧野社長
そうですね。家は限界集落にあっても、若い子ども達がみんな里に降りてきてしまっていますね。それで高齢の親はまだそこに残っている、という構図ですね。
小林社長
そうするとね、今度は「自分の庭を守る人がいない」、「庭が荒れ放題になっちゃう」ということになって、どうするんだって、さっきの話になっちゃう。
そうなると、さっきも言ったように「里の人達が助ける」っていう、相互扶助の考え、おなじ地域なんだから、一緒に山も守りましょうよっていう話にならざるを得なくなる。
必然的に農業の分野なんかもそうですよね、棚田がいっぱいあって「もう田んぼやりきれない」となると、「じゃあ任すよ」っていう話もあるんだけど、任されたその人も高齢な訳ですよ。その任された人までもが里の方に行っちゃうと、もう本当に誰も引き受け手がいないんですよね。
だからこれからは里の人間が喜び勇んで限界集落に行けるような仕組みが必要になってきます。
そうなると、さっきも言ったように「里の人達が助ける」っていう、相互扶助の考え、おなじ地域なんだから、一緒に山も守りましょうよっていう話にならざるを得なくなる。
必然的に農業の分野なんかもそうですよね、棚田がいっぱいあって「もう田んぼやりきれない」となると、「じゃあ任すよ」っていう話もあるんだけど、任されたその人も高齢な訳ですよ。その任された人までもが里の方に行っちゃうと、もう本当に誰も引き受け手がいないんですよね。
だからこれからは里の人間が喜び勇んで限界集落に行けるような仕組みが必要になってきます。
竹本
そうですよね。そういう仕組みはどんなものをお考えなんでしょうか?
小林社長
例えばちょっとお金もらえるとかっていう風な仕組みで良いと思うんですね。
日本全国抱えている課題はどこも一緒だと思うんです。
もしくはそんな補助金など出さず、「思いきって山に戻す」というのもアリだと思っています。
日本全国抱えている課題はどこも一緒だと思うんです。
もしくはそんな補助金など出さず、「思いきって山に戻す」というのもアリだと思っています。
竹本
「山に戻す」って、具体的にはどういうことでしょうか?
小林社長
田んぼや畑を、植林なんかで広葉樹を植えて、山に戻す。文字通りの意味ですよ。
本当に昔は人間が勝手に山奥分け入って、開拓したんでしょ。住むために田んぼまで作ったわけです。それをこの機会にもう一回山に戻す。
本当に昔は人間が勝手に山奥分け入って、開拓したんでしょ。住むために田んぼまで作ったわけです。それをこの機会にもう一回山に戻す。
竹本
お金かかりそうですね!
小林社長
お金は掛かるけど、将来的に見れば、長期的に見ればコストは安くつくかもしれません。例えば田んぼが放置されたが故にそれが土砂崩れ等の災害に繋がったり、保水力が無くなったり、というんであれば、もう一回山に戻してあげることも真剣に考えた方が良い時代に来ていると思うんです。
とにかく、今のままではダメですよね。里のヒトなりモノなりカネを思い切ってつぎ込まなきゃダメな時期に来ていると思うんです。
とにかく、今のままではダメですよね。里のヒトなりモノなりカネを思い切ってつぎ込まなきゃダメな時期に来ていると思うんです。
竹本
なるほど。いきなり深い話ですね。本当そうですよね。
左から筆者(竹本)、須弥山合同会社 牧野社長、株式会社武蔵野酒造 小林社長。のっけから天然水の話が出ないのはいつものことだが、日本酒の話すら出ず、「地方とその再生」というテーマになった。熱い。

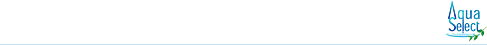
竹本 大輔