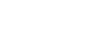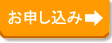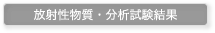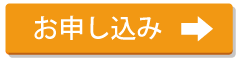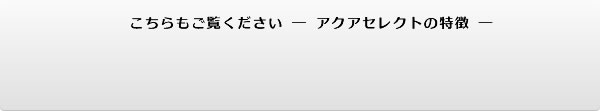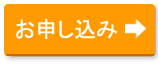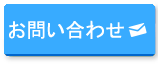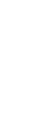水のはなし
天然水の人びと
アクアセレクトGMの竹本大輔による水紀行
第13回 浦谷地区の高山さん サツマの切り干しなど
これが「あられ炒り」。あまり入れると膨らむので大変なことになるとのこと。「ちぃとしか入れたらアカンよ」と教えていただいた。

上部が開閉する。単純なギミック、そして年季が入っていることに、顔がほころぶ。

利通さん
これで炒りましたんや。
竹本
これはゴマ炒り器の大きい版ですね。今でも売っているものなんですか?
利通さん
近くのホームセンターで売ってると思うよ。
竹本
そうですか!帰りに買って帰ろうっと(笑)!
利通さん
あんまり強火はアカンよ。弱火でやると上手いこと炒れるよ。でも粉が落ちるでなぁ。
ちかさん
電子レンジでも出来るとか聞いたけど、これで炒るのが一番やと思うよ。
ちかさん:
これにあられを入れて閉じて持って行くと、しょっちゅう親が炒ってくれましたな。おやつ代わりに食べてましたわ。「サツマの切り干し」もよう食べたわ。甘くて美味しかったなぁ。
※著者注:サツマイモの切り干しとは「干し芋」のこと。この地域では、サツマイモの収穫後、各家庭で作り、おやつとして常備していたそうだ。
※著者注:サツマイモの切り干しとは「干し芋」のこと。この地域では、サツマイモの収穫後、各家庭で作り、おやつとして常備していたそうだ。
竹本
市販品はいまでも人気ありますもんね。
ちかさん
あんな(市販品のように)薄く切らんと、もっと厚く切りますんさ。
ちかさん
「サツマの切り干し」はようけ作ったもんさ。昔は庭にいっぱい広げて干したもんさ。
竹本
デンプンが白い粉になって美味しいですよね。
ちかさん
そうさ。あれはお天道様に干して、真っ白にしたるんさ。あんまり干したらカンカンになるから、ちょうど真っ白に粉が吹きよるころに引き上げるんさ。
サツマが収穫出来たら、そこからちょっと寒くなったらやってましたわな。
サツマが収穫出来たら、そこからちょっと寒くなったらやってましたわな。
ちかさん
真っ白に粉が吹いてねっとりとしてますんさ。芋の種類の「べにあずま」はねっとりしてる感じがするけどなぁ。兄嫁さんがずっとしてましたなぁ。
竹本
手作りは旨そうですね~!
ちかさん
すこし、自分でやりはったらええわ。あんなん、蒸して切って日向に干しといたらエエねん。椎茸干すやつありますやろ。あの網戸を横にしたようなものに置いとくと上手く乾きますんや。
親が並べてるやつの端っこを食べたったりしてな(笑)
親が並べてるやつの端っこを食べたったりしてな(笑)
利通さん
子どもがおったりするとおやつにしたったりするけど、子どもの数が減ってるとやる家はのう(無く)なってくるわな。
ウチはひ孫までおりますからな。作った野菜なんかも時々来ては持って帰りおるんよ。それで、野菜なんかも甘いっちゅうんやわ。
ウチはひ孫までおりますからな。作った野菜なんかも時々来ては持って帰りおるんよ。それで、野菜なんかも甘いっちゅうんやわ。
ちかさん
私らずっとウチで食べてるから分からんけど、息子らは美味しい言うてくれんねん。
竹本大輔
ここ大台町や旧宮川村の方はエエもんを食べてはりますもんね。
ちかさん
エエもんとはちゃうけど、昔ながらのもんを食べてるからな。
竹本
いま、「あられ」なんかも塩の味がまず先にしますもんね。
ちかさん
そうやなぁ、やっぱり自然のものがエエわな。水もキレイしなぁ。
竹本
そうですね!
ちかさん
写真はあんまりやめてや(笑)。
別嬪(べっぴん)さんでないからなぁ。
白菜よかったら持って行きなぁ。
別嬪(べっぴん)さんでないからなぁ。
白菜よかったら持って行きなぁ。
竹本
いやぁ別嬪さんですよ!白菜ありがとうございます!
利通さん、ちかさんと。「あられ」を袋にいっぱい頂いた。

静かな佇まいを見せる浦谷川。良いお水と、よい食材、そして温かな人たち。昔ながらの製法があり、それを連綿と受け継いでいく人たちがいる。アクアセレクトの水質も製品化も、かのように守り続けていきたい。

編集後記
さっそく帰り道、ホームセンターで「あられ炒り」を購入。店員さんに聞くと、サッと案内してくれた。地域に根付く食文化だと実感。

言われたように「ちぃとだけ入れて」弱火で炒る。

だんだん「あられ」らしくなってきた。

見事に「あられ」が完成。食べると、もち米が持つ自然な甘みが口いっぱいに広がる。子どもたちが集まってきてすぐになくなった。ちょっと「ちぃ」と過ぎたか?

「あられ」がここまで美味しいものだとは、初めての体験であった。
あまり上等なあられを食べたことがないからかもしれないが、今まで食べたことのある市販品とは別物であった。
塩を振らずとも、砂糖醤油と絡めずとも、手作りの餅本来の甘みと旨みが凝縮している。
こんな旨いものを、竈(くど)の熾火(おきび)で炒るなんて、なんと贅沢なことか。
きっと土間で炒っている間、子らはまだかと親に催促し、親は子どもらに「もうちょっとよ」と、笑顔で応えたのだろう。
調理が終わり、少しばかりの熱気の残る土間(どま)が、ほんわりと再び暖まったことであろう。
親から子へ、子から孫へ受け継いでいく食文化。
地域で語り継いでいく食文化。
先祖から受け継いだ素晴らしい森のめぐみをお届けするアクアセレクトは、その食文化の一端を担う。
そんな私たちこそが、この素晴らしい食文化の架け橋であり続けたいと願う。
あまり上等なあられを食べたことがないからかもしれないが、今まで食べたことのある市販品とは別物であった。
塩を振らずとも、砂糖醤油と絡めずとも、手作りの餅本来の甘みと旨みが凝縮している。
こんな旨いものを、竈(くど)の熾火(おきび)で炒るなんて、なんと贅沢なことか。
きっと土間で炒っている間、子らはまだかと親に催促し、親は子どもらに「もうちょっとよ」と、笑顔で応えたのだろう。
調理が終わり、少しばかりの熱気の残る土間(どま)が、ほんわりと再び暖まったことであろう。
親から子へ、子から孫へ受け継いでいく食文化。
地域で語り継いでいく食文化。
先祖から受け継いだ素晴らしい森のめぐみをお届けするアクアセレクトは、その食文化の一端を担う。
そんな私たちこそが、この素晴らしい食文化の架け橋であり続けたいと願う。
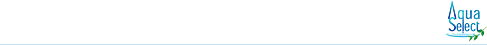
竹本大輔