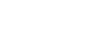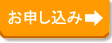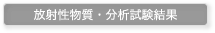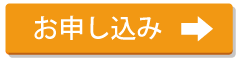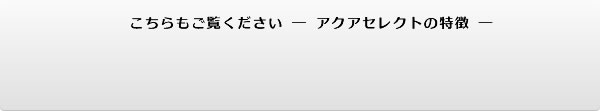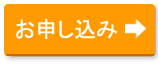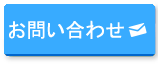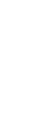水のはなし
天然水の人びと
アクアセレクトGMの竹本大輔による水紀行
第28回 良い水を育む森そして林業編6 最終回
お話は多岐にわたった。この大台町の林業にとって、そして日本の林業にとって、アクアセレクトの取り組みが少しでも役立てば、と思う。

良い水を育む森そして林業 最終回
竹本
これからの林業の展望をお聞かせください。
岡本
個人的にはスギ・ヒノキの人工林戦後50年間違った選択をしてきたわけではなく、貴重な財産だと考えています。
この財産を上手く引き継いで、経済的な価値そして環境的な価値をさらに向上させていきたいですね。
同じような問題を繰り返さない、スギの皆伐した後にスギを植えてはダメなところは地域の中でそこに応じた
科学的な根拠、そして長期ビジョンと短期目標の設定、こういったことをやっていくこと。
この財産を上手く引き継いで、経済的な価値そして環境的な価値をさらに向上させていきたいですね。
同じような問題を繰り返さない、スギの皆伐した後にスギを植えてはダメなところは地域の中でそこに応じた
科学的な根拠、そして長期ビジョンと短期目標の設定、こういったことをやっていくこと。
竹本
岡本さんにまだお孫さんはいらっしゃらないと思うんですが、そこまで考えていただいていることを思うと、お孫さんまでもが幸せな感じがしますよね(笑)
岡本
あと言えることは、林業の展望を語るときに林業界だけで集まらないで、いろいろな業界で集まった方が良いということですね。
竹本
そこも多様性が必要なんですね。どういった業界と手を組むのが面白いですか?
岡本
家具業界、機材メーカーさん、製紙業界、なんかもあると思います。流通業界なんかも面白いと思います。
アメリカには森林ファンドというものがあるんですが、これからは金融業界なんかも面白いですね。
アメリカには森林ファンドというものがあるんですが、これからは金融業界なんかも面白いですね。
竹本
ぼくらの業界としては水の業界としては森林にお世話になりっぱなしなんで。
アクアセレクトのお客様に向けて何かメッセージを。
アクアセレクトのお客様に向けて何かメッセージを。
岡本
そうですな…
ここ大台町のような中山間地(ちゅうさんかんち)というのは、緑豊かで渓流があって、なにか自然豊かというイメージがあると思うんです。
ところが今そうじゃない。
「鹿害」の問題が深刻なんです。
原生林の植生はもちろん、林床を食べ、その土地を裸地化していきます。
人工林においても、50年生の木も樹皮が剥がされて食われてしまって、建材価値がなくなってるんですね。
環境的な被害と経済的な被害が同時進行しているんです。
このまま放っておくと、危機的な状況にあるということです。
日本は水が豊かと言われていますが、最悪のシナリオとして、このままだと森が無くなって緑が全部枯れてしまって、土が見えて、土砂崩れが多発して…となってしまう可能性が十分あります。
緑は積極的に守っていかないといけない、放っておくと緑は失われてしまうものだということをご理解いただきたいと思います。
ここ大台町のような中山間地(ちゅうさんかんち)というのは、緑豊かで渓流があって、なにか自然豊かというイメージがあると思うんです。
ところが今そうじゃない。
「鹿害」の問題が深刻なんです。
原生林の植生はもちろん、林床を食べ、その土地を裸地化していきます。
人工林においても、50年生の木も樹皮が剥がされて食われてしまって、建材価値がなくなってるんですね。
環境的な被害と経済的な被害が同時進行しているんです。
このまま放っておくと、危機的な状況にあるということです。
日本は水が豊かと言われていますが、最悪のシナリオとして、このままだと森が無くなって緑が全部枯れてしまって、土が見えて、土砂崩れが多発して…となってしまう可能性が十分あります。
緑は積極的に守っていかないといけない、放っておくと緑は失われてしまうものだということをご理解いただきたいと思います。
竹本
ちなみに鹿が増えたのはどういった原因なんでしょうか?
岡本
3つ原因があると言われています。
まず温暖化。温暖化で積雪量が減ったことが大きな要因ですね。
鹿は越冬します。鹿はその特性により、鹿の足の高さよりも雪があると動けなくなって死んでしまう。
ところが雪が降らなくなって小鹿の越冬率が飛躍的に伸びたんですね。
第2に天敵がいなくなった。ニホンオオカミなどの天敵がいません。
第3に狩猟圧(しゅりょうあつ)の低下です。
猟友会の方も高齢化しています。それに加えて、鹿肉などが高付加価値だったのが、価値が下がっている。
結局のところ、林業イコール木材生産だけ考えていてはダメな時代なんです。
合わせて鹿問題を考えることが中山間地域においては必要です。
まず温暖化。温暖化で積雪量が減ったことが大きな要因ですね。
鹿は越冬します。鹿はその特性により、鹿の足の高さよりも雪があると動けなくなって死んでしまう。
ところが雪が降らなくなって小鹿の越冬率が飛躍的に伸びたんですね。
第2に天敵がいなくなった。ニホンオオカミなどの天敵がいません。
第3に狩猟圧(しゅりょうあつ)の低下です。
猟友会の方も高齢化しています。それに加えて、鹿肉などが高付加価値だったのが、価値が下がっている。
結局のところ、林業イコール木材生産だけ考えていてはダメな時代なんです。
合わせて鹿問題を考えることが中山間地域においては必要です。
竹本
なるほど。では間伐やって林床に光を当てて下草を増やす、なんてことをやってると鹿害を増やすことになるので、鹿害対策を含めて考えないといけないという事なんですね。
岡本
そうなんです。
竹本
鹿問題以外にはどんな問題がありますでしょうか?
岡本
虫害の問題も大きいですね。
ナラ類にはナラノナガキクイムシが付きます。
またマツ類にはマツクイムシ、そしてスギにはアカネトラカミキリが付いて住宅建材の価値を落としてしまいます。
もともと原生林にはコナラ林というものは存在しません。コナラはまばらに育ってくるんですね。
それが人工林となるとコナラをまとめて林にしてしまう。
それは良いのですが、植えた後放ったらかし、というのがダメなんです。
その尻拭いが今きているということです。
ナラ類にはナラノナガキクイムシが付きます。
またマツ類にはマツクイムシ、そしてスギにはアカネトラカミキリが付いて住宅建材の価値を落としてしまいます。
もともと原生林にはコナラ林というものは存在しません。コナラはまばらに育ってくるんですね。
それが人工林となるとコナラをまとめて林にしてしまう。
それは良いのですが、植えた後放ったらかし、というのがダメなんです。
その尻拭いが今きているということです。
竹本
価値観も多様化している現代においては、都市部の方も一緒になって考えることが必要ですね。
一杯のコップの天然水から、遠く森林に思いを馳せていかなければなりませんね。
一杯のコップの天然水から、遠く森林に思いを馳せていかなければなりませんね。
竹本
今の子どもさん世代へのメッセージをお聞かせください。
岡本
山を歩いていると、いろいろな木や森に出会えます。その木や森の違いをよく見てほしいと思います。森や自然というものにそれぞれどういった違いがあるのか、これは簡単に見分ける事が出来ると思うんですね。比較をどんどんしていってほしいと思います。
それがひいては、社会の多様性を学ぶ第一歩だと思うんです。
それがひいては、社会の多様性を学ぶ第一歩だと思うんです。
竹本
なるほど自然のディティールを見るということですね。
子どもさんも森の中に入っていって元気に遊ぶと、鹿も里に降りてこない気がしますもんね(笑)
今日は長時間にわたり貴重なお話をありがとうございました!
子どもさんも森の中に入っていって元気に遊ぶと、鹿も里に降りてこない気がしますもんね(笑)
今日は長時間にわたり貴重なお話をありがとうございました!
見上げれば、いつの間にか青い空。
土くれの感覚、石ころ、そして木の根。地面にへばり付いて五感を働かし没頭した一日。
吹き渡る風が爽やかだった。
土くれの感覚、石ころ、そして木の根。地面にへばり付いて五感を働かし没頭した一日。
吹き渡る風が爽やかだった。


彼らは木に触れ、そして土に触れ、森作りを楽しんだ。
この経験がこれからの日本の森林を守り、そして未来に向けて、豊かな森を育む原動力になってくれればと、願う。
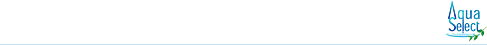
竹本大輔