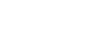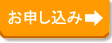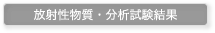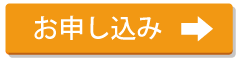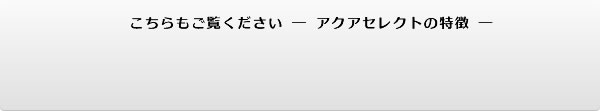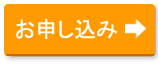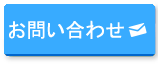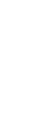水のはなし
天然水の人びと
アクアセレクトGMの竹本大輔による水紀行
第24回 良い水を育む森そして林業編2
チームに分かれて、がんばるぞ!

まだまだ余裕。

説明が始まるや否や、真剣そのもの。作業量の多さ、そして困難さを目の当たりにする。

良い水を育む森そして林業編2
竹本
これからの大台町に適した林業というものってどんなものなんでしょうか?
文献で読んだのですが、川中島の戦い、つまり1560年ごろまでは、大台町旧宮川村地区の最奥である大杉地区から伊勢神宮遷宮のための御用檜(ごようひのき)を切り出してた、とあって結構歴史もあるんだなぁと。
文献で読んだのですが、川中島の戦い、つまり1560年ごろまでは、大台町旧宮川村地区の最奥である大杉地区から伊勢神宮遷宮のための御用檜(ごようひのき)を切り出してた、とあって結構歴史もあるんだなぁと。
岡本
大台町に適した林業というのは結構難しい質問ですな(笑)
人工林というのが大台町の民有林の約50%を占めています。
例えばこの50%に広葉樹の森を作ろうします。
これもこの地に適した木を植えるとします。
人工林というのが大台町の民有林の約50%を占めています。
例えばこの50%に広葉樹の森を作ろうします。
これもこの地に適した木を植えるとします。
竹本
あの京大の高田先生(自然配植技術協会会長)の自然配植ですね。
※以前岡本さんにご紹介いただき、筆者も「自然配植研修」なるものを1泊2日で受講したことがある。
※以前岡本さんにご紹介いただき、筆者も「自然配植研修」なるものを1泊2日で受講したことがある。
岡本
そうです。そうです。
あの手法は、例えば1ヘクタールの山に50種類から80種類を、その樹木の生育環境に応じて植え分けていくわけですよね。
あの手法は、例えば1ヘクタールの山に50種類から80種類を、その樹木の生育環境に応じて植え分けていくわけですよね。
竹本
そうでしたね。
岡本
では大台町の人工林の約半分を占めているスギ、ヒノキというたった2つの樹種が、そもそも適した場所に植わっているか?ということが疑問として出てくる訳です。
竹本
確かにそうなりますね。
岡本
現在の間伐には、長伐期(ちょうばつき)という100年生や80年生を育てていこうね、という施策があります。
これには矛盾が生じてくるんですね。
何かというと、つまり適していないところにある今の50年生のスギ・ヒノキというものがあるとします。これは実際にあるんですね。
これらにも同じようにお金を掛けて、間伐をして、もちろん長伐期という訳ですから長い時間を掛けて育てるということが、果たして費用対効果として見合っているのか、という矛盾です。
これについては、今この時期によく考え直さないといけません。
これには矛盾が生じてくるんですね。
何かというと、つまり適していないところにある今の50年生のスギ・ヒノキというものがあるとします。これは実際にあるんですね。
これらにも同じようにお金を掛けて、間伐をして、もちろん長伐期という訳ですから長い時間を掛けて育てるということが、果たして費用対効果として見合っているのか、という矛盾です。
これについては、今この時期によく考え直さないといけません。
竹本
なるほど。
岡本
つまり施業をする場所と、内容、そして長期のビジョンを持って、目的を地域全体で共有した上で、行政/研究者/森林所有者/林業従事者が、ここ大台町の森をどのように作り替えていくのかを一緒になって考えていく時期やな、と思っています。
全ての人工林に対して、スギやヒノキの大径木(たいけいぼく)を作っていく、ということでよいのか?ということです。
しかも、それが適地かどうか?ということも検討し直さなければならないと感じています。
全ての人工林に対して、スギやヒノキの大径木(たいけいぼく)を作っていく、ということでよいのか?ということです。
しかも、それが適地かどうか?ということも検討し直さなければならないと感じています。
竹本
なるほど。過去の施策含めて難しいものなんですね…
そういったことって大台町含め日本全国で活発に議論されていることなのでしょうか?
そういったことって大台町含め日本全国で活発に議論されていることなのでしょうか?
岡本
いや、それもまだまだです。
適地性判断というのは、学術的な根拠がなかなか示されていないんですね。
要するにスギやヒノキの適地か?もしくはケヤキの適地か?ということを判断するには時間がかかるのです。
適地性判断というのは、学術的な根拠がなかなか示されていないんですね。
要するにスギやヒノキの適地か?もしくはケヤキの適地か?ということを判断するには時間がかかるのです。
竹本
そうですね。ケヤキなんかはものすごく時間がかかると聞きました。
岡本
そうなんです。
そういう時間がかかるものなんで、経験則でしかモノが言えないということになってしまうんですね。
そういう時間がかかるものなんで、経験則でしかモノが言えないということになってしまうんですね。
竹本
なるほど、職人技みたいになってしまうということですね。
岡本
そうなんです。その経験則に頼らざるを得ないものが全国に通用するのか?という問題にもぶち当たります。
そういった意味で難しいとなってしまうんですね。
そういった意味で難しいとなってしまうんですね。
竹本
うーん、なるほど。
岡本
ただここ大台町では、広葉樹の森を作ることを通じて、大台町ならではの「適地性判断」を行っています。
その発展形として、平成22年度から大台町の事業のもとで、人工林の適地性判断技術の習得を行っています。
その検証結果を学術的に補完していただく為に京都府立大学に研究を委託し、森林立地評価技術が確立されつつあります。それを広葉樹、つまりたとえばサクラなどに置き換えて同じ失敗をする可能性もありますよね。
そういう意味では、同じ失敗を未来の世代に向けて残してしまうので、十分注意しながら取り組んで行かないとダメだと思っています。
その発展形として、平成22年度から大台町の事業のもとで、人工林の適地性判断技術の習得を行っています。
その検証結果を学術的に補完していただく為に京都府立大学に研究を委託し、森林立地評価技術が確立されつつあります。それを広葉樹、つまりたとえばサクラなどに置き換えて同じ失敗をする可能性もありますよね。
そういう意味では、同じ失敗を未来の世代に向けて残してしまうので、十分注意しながら取り組んで行かないとダメだと思っています。
竹本
植物学的な要素、また地理学的な要素、その地域の伝統…たしかに複雑ですが、この大台町それも地域を限定した形では先行事例を元に適地性判断が十分機能しているということですね。
広葉樹の苗を植え付けるための穴を掘り、そしてその苗をバケツの水に浸し、植えつけていく。

植えつけた後は、ツルハシの柄でしっかりと土を固め、根を活着させる。
大きくなることを願って。
大きくなることを願って。

ツルハシを、そして手を使いながら。
土の匂い、木の枝ぶり、そして風の温もり。
五感を働かせながら。
土の匂い、木の枝ぶり、そして風の温もり。
五感を働かせながら。

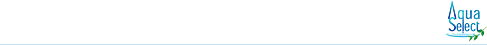
竹本大輔