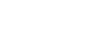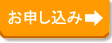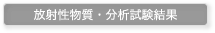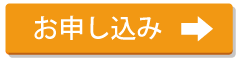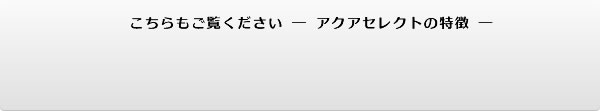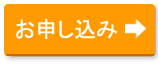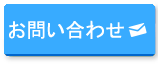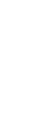水のはなし
天然水の人びと
アクアセレクトGMの竹本大輔による水紀行
第23回 良い水を育む森そして林業編1
良い水を育む森
私たちアクアセレクトでは、定期的に植樹を行っている。水源涵養林(すいげんかんようりん)としての森林保全だ。そんな水源の森を毎日見つめ、そして考え、守り続けている組織がある。それが三重県多気郡大台町旧宮川村にある「宮川森林組合」だ。その森林組合の林業振興課長である岡本宏之さんを訪ねた。
先日実施したアクアセレクトスタッフによる植栽体験。この地域で採取した種から育てた「地域性苗木」を用い、自然配植という技術を用いた。

背後に見える網は鹿除けのための網。「パッチディフェンス」という防鹿技術。鹿にこのパッチを檻と勘違いさせ、侵入を防ぐ技術だ。一口に「植林」「植栽」と言っても、非常に奥が深い。

宮川森林組合の岡本宏之さん。森作りに対する熱い思いを聞かせていただけた。

竹本大輔
本日はどうぞよろしくお願い致します。
まず、岡本さんのご経歴、林業に従事することになったキッカケなんかを教えてください。
また宮川の展望、また我々企業と林業の関わり合いなんかを教えていただけますでしょうか?
まず、岡本さんのご経歴、林業に従事することになったキッカケなんかを教えてください。
また宮川の展望、また我々企業と林業の関わり合いなんかを教えていただけますでしょうか?
岡本宏之さん
(以下敬称略)
(以下敬称略)
よろしくお願いします。
竹本
ちなみに岡本さんはこちら大台町のお生まれですか?
岡本
そうです。生まれは宮川村の「江馬(えま)」なんです。
竹本
大台町旧宮川村の銀座通りの江馬ですね(笑)
岡本
そうです。都会っ子ですな(笑)
江馬の学校出て、工業系の学校出て、機械科を出たんです。それで大阪のメーカーに入って5 年勤めて、それで実家に帰ってきたんです。大阪は香里園(こうりえん)に住んでいました。その後は南津守(みなみつもり)に住んでいましたね。
江馬の学校出て、工業系の学校出て、機械科を出たんです。それで大阪のメーカーに入って5 年勤めて、それで実家に帰ってきたんです。大阪は香里園(こうりえん)に住んでいました。その後は南津守(みなみつもり)に住んでいましたね。
竹本
ぼくは津守の自動車学校の卒業生ですよ(笑)!
雑多とした良いところですよね。
では地元に帰ってこられて森林組合に入られたんですね。
雑多とした良いところですよね。
では地元に帰ってこられて森林組合に入られたんですね。
岡本
そうです。
ただ、こちらに帰ってきて、大阪のメーカーと森林組合の仕事にギャップをだいぶ感じたんです。
ただ、こちらに帰ってきて、大阪のメーカーと森林組合の仕事にギャップをだいぶ感じたんです。
竹本
どのあたりですか?
岡本
一言では難しいですけど、大阪のメーカーのみならず企業というのは、熾烈な競争の中で少しでも利益を追求するという環境ですよね?その環境と、こちらの時間の流れがゆるやかな環境とにギャップを感じましたね。
竹本
そうかもしれませんね。
ちなみに森林組合に入られて何年目なんですか?
ちなみに森林組合に入られて何年目なんですか?
岡本
平成10 年の入社です。
竹本
この10 年間で林業は変わったのでしょうか?
岡本
一番変わったのは、そうですね…平成24 年4 月から森林法が変わったんです
今まで人工林の育てる経費というのは補助金なんかでほとんど賄われていたんです。
もちろん、そういった補助金への依存度がすごく高くなっています。
ただそういったことも平成24 年3 月末までなんです。
平成24 年4 月からは利用間伐といって、木を売り上げて、もちろん補助金なんかも使ってですけど、やっていきなさい、ということに変わりました。
今まで収入の大半を公のお金に依存していた業界が、間伐材の売り上げと補助金の両方の収入で遣り繰りしなさい、ということになったんですね。
林業を取り巻く環境が大きく変化するということです。
今まで人工林の育てる経費というのは補助金なんかでほとんど賄われていたんです。
もちろん、そういった補助金への依存度がすごく高くなっています。
ただそういったことも平成24 年3 月末までなんです。
平成24 年4 月からは利用間伐といって、木を売り上げて、もちろん補助金なんかも使ってですけど、やっていきなさい、ということに変わりました。
今まで収入の大半を公のお金に依存していた業界が、間伐材の売り上げと補助金の両方の収入で遣り繰りしなさい、ということになったんですね。
林業を取り巻く環境が大きく変化するということです。
竹本
どのような背景でこのような法律改正が行われたのでしょうか?
岡本
全国の平均林齢が50 年生になってきて収穫段階になってきた、というのが一番大きいでしょうね。
ただ、個人的に感じているのは、間伐材を切り捨てていく林業をいつまでやったらええんや?ということでしょうね。
その間、お金は出っぱなしでしょう。
全国の平均樹齢が50 年もたっているんだから、いつまでも甘えずにやりなさい、ということなんだと思っています。
ただ、個人的に感じているのは、間伐材を切り捨てていく林業をいつまでやったらええんや?ということでしょうね。
その間、お金は出っぱなしでしょう。
全国の平均樹齢が50 年もたっているんだから、いつまでも甘えずにやりなさい、ということなんだと思っています。
竹本
ぼくチラッと速水林業さんの本「日本林業を立て直す」を読みました。そこには、確かにここの林業ではなく尾鷲(おわせ、同じく三重県南部)の林業ですけれども、「長期的な視点を持って経営しなさい」ということが書かれていました。
岡本
そうですね。
林業の形態について、その地域ごとで特徴があっても良いと思っているんです。
農業については結構そういうのがあると思います。例えば、落花生というと千葉県が有名な産地ですよね。
農業と同じように林業においてもスギやヒノキにも適した産地というのがあるんですね。
林業の形態について、その地域ごとで特徴があっても良いと思っているんです。
農業については結構そういうのがあると思います。例えば、落花生というと千葉県が有名な産地ですよね。
農業と同じように林業においてもスギやヒノキにも適した産地というのがあるんですね。
竹本
いわゆる「林業適地」という考え方ですよね。
岡本
そうです。
秋田杉とか吉野杉、そして尾鷲檜が有名ブランドですね。
つまり同じような尾鷲、吉野、秋田と同じような競争をしていけるのか?ということなんです。
これは難しいことなんですね。
山の環境、歴史的な背景、そして地域に馴染んだ伝統的な技術があります。
それを活かした林業を提案しながらやっていかなアカンと思っています。
つまり「考える林業」でないとダメだと思っています。
秋田杉とか吉野杉、そして尾鷲檜が有名ブランドですね。
つまり同じような尾鷲、吉野、秋田と同じような競争をしていけるのか?ということなんです。
これは難しいことなんですね。
山の環境、歴史的な背景、そして地域に馴染んだ伝統的な技術があります。
それを活かした林業を提案しながらやっていかなアカンと思っています。
つまり「考える林業」でないとダメだと思っています。
竹本
なるほど、確かに。ちょっと言葉は悪いですけれど、なんにも考えんと補助金じゃぶじゃぶ使ってやってた林業からは脱却しないとダメってことですね。
岡本
そうなんです。
ぼーっとしてたら淘汰もされる時代ってことになります。だからこそこれをチャンスと捉え、そこに面白みを感じられるようになって行かないとダメだと思って日々、苦悩しています。
ぼーっとしてたら淘汰もされる時代ってことになります。だからこそこれをチャンスと捉え、そこに面白みを感じられるようになって行かないとダメだと思って日々、苦悩しています。
竹本
前向きだなぁ~(笑)
すごく安心しました!
すごく安心しました!
急な斜面を登る。林業基本とは、山を歩く、チェーンソーを担いで山を登ること、という話を聞いた。チェーンソーは持ってはいないが、苗の入った重たいケースを担ぎ上げる。うっかりするとずり落ちそうなそんな斜面だ。

防鹿柵(ぼうろくさく) の中に入り、植栽の方法を学ぶ。

ムラサキシキブは日陰を作るように、イロハモミジは手のひらを横に伸ばすように…。
数多くの樹種、その樹種ごとに役割、そして植え方の違いがあることを体験する。
数多くの樹種、その樹種ごとに役割、そして植え方の違いがあることを体験する。

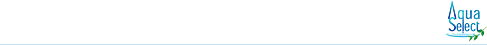
竹本大輔