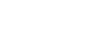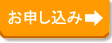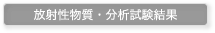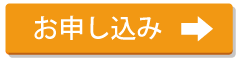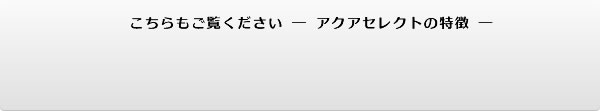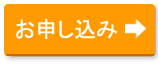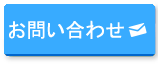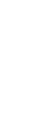水のはなし
天然水の人びと
アクアセレクトGMの竹本大輔による水紀行
第5回 元坂酒造さま 寒仕込みについて
寒仕込みについて
竹本
寒の時期の水の良さだとか、この時期ならではの仕込みをお聞かせいただきたいです。
元坂
寒仕込みというのが、日本酒の世界では一般的なんですね。
竹本
それをグーグルで検索して直接お電話しました(笑)。
元坂
寒の時期は雑菌が繁殖しにくいのと、醗酵が進みにくいというのがあるんですね。
早く酒になりすぎるんで、この時期でないとだめなんです。
いわゆる、微生物を使う食文化ですね。
それを使うには寒の時期や、と昔の人が考えたんだと思うんですね。酒も微生物ですね。それが第一やと思います。
あと、水も腐りにくい。宮川の水は軟水ですよね。飯南(いいなん)の方に行くと硬水で腐りにくい、という水があるんですが、抗菌性が強いと酒造りに向かない。
菌を活かさないといけないんですね。それを上手く操作してやらないとだめなんで、寒の時期なんですね。
大寒に向けて一番いい酒を仕込むんですね。
これから3週間くらい徹夜が続くんです。徹夜と言っても夜の10時くらいまでやって、午前1時に起きて、また仕込む。
早く酒になりすぎるんで、この時期でないとだめなんです。
いわゆる、微生物を使う食文化ですね。
それを使うには寒の時期や、と昔の人が考えたんだと思うんですね。酒も微生物ですね。それが第一やと思います。
あと、水も腐りにくい。宮川の水は軟水ですよね。飯南(いいなん)の方に行くと硬水で腐りにくい、という水があるんですが、抗菌性が強いと酒造りに向かない。
菌を活かさないといけないんですね。それを上手く操作してやらないとだめなんで、寒の時期なんですね。
大寒に向けて一番いい酒を仕込むんですね。
これから3週間くらい徹夜が続くんです。徹夜と言っても夜の10時くらいまでやって、午前1時に起きて、また仕込む。
竹本
電話で「徹夜が続くんです」「いや、ちょっとだけお話を…」というやり取りが…。そんな時に取材に来てしまいました(笑)
元坂
(笑)
竹本
米の産地って世界中にあると思います。中国もそうですし、東南アジアなんかもそうですが、なぜ日本のみでこういった日本酒の醸造が行われているんでしょうか?やはり寒暖の差ですか?
元坂
寒暖の差もありますが、湿気の問題が大きいんじゃないかと思います。大陸は乾燥してるんですね。麹(こうじ)って日本では粒状麹(りゅうじょうこうじ)って言うんですけど、大陸の方では、餅鞠(へいぎく)にしてやらないと、うまく醗酵しないんです。
熟れ寿司(なれずし)とか、やはり湿度が高い日本ならではの独特の文化ですね。
熟れ寿司(なれずし)とか、やはり湿度が高い日本ならではの独特の文化ですね。
中を覗き、香りをかいでみる。甘く自然な素晴らしい香りがする。

タンクの中で醗酵している様子がうかがえる。酒は生き物。

山廃(やまはい)仕込みのタンクの前での元坂社長。酒造りの人たちの親方を「杜氏(とうじ)」と呼ぶ。名杜氏をもってしても、山廃は搾ってみないと分からない。

この「寒の時期」という「天の時」、そして東アジア温帯モンスーン地帯、大台町という多雨地域という「地の利」、そして名杜氏はじめ酒蔵の人たちの「人の和」。それらが一体となって名酒が生み出される。どぶろくのお話もお伺いしたが、それを入れるのはこういう作用があるんですよ、と非常に明確にお答えいただいた。化学変化、微生物などにも明るくないと杜氏は務まらないのだろう。
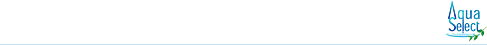
竹本大輔