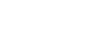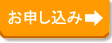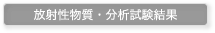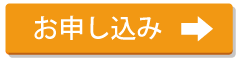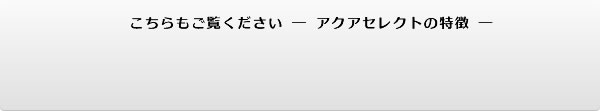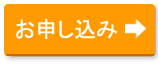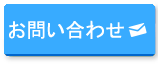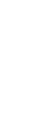水のはなし
天然水の人びと
アクアセレクトGMの竹本大輔による水紀行
第12回 浦谷地区の高山さん あられの作り方、食べ方
「あられ」の作り方、食べ方
竹本
この寒の時期の農作業はどういったものがありますか?
利通さん
「寒起し(かんおこし)」というのものがあるわな。「寒起し」しておくと、土の表面に出てきた虫が冷えて死んでいくわな。うちももう鋤(す)いてあるけどな。
ちかさん
お待たせしました。こんなして私ら作るんさ。
持ってきていただいた「あられ」。とても固く、自然なクリーム色をしている。

サイズはこれくらい。これをじっくりと炒ると、それはそれは美味しい「あられ」になる。

竹本
ちょうどパスタのような感じですね。
ちかさん
色を入れたりするのもあるんさ。ウコンやクチナシで黄色、アオサで青色とか、おめでたい色を付けるんさ。
ちかさん
これを油で揚げるとようけ膨らむでな、ちぃとしか(ちょっとしか)入れたらアカン。
竹本
なるほど。乾燥させるときは薄く切ってから乾燥させるんですか?
ちかさん
道に筵(むしろ)を広げて乾かすんです。
ただ乾かしてるだけやと、乾燥しすぎてヒビが入ってきますんで、新聞紙かなんかを上に掛けとくんです。
ただ乾かしてるだけやと、乾燥しすぎてヒビが入ってきますんで、新聞紙かなんかを上に掛けとくんです。
竹本
なるほどこの時期ならではですね。
利通
この時期に作っておくと、カビが生えにくいんさ。
竹本
お水とお天とさんと風と乾燥具合とがちょうどいいんですね。
利通さん
手を入れなイカンで面倒くさいんやけどな。
ちかさん
手を入れてやると万遍(まんべん)なく乾くもんで、エエんやわ。
竹本
大変な手仕事ですね
ちかさん
昔はこういう「あられ」をいーっぱい作って、それこそ棚一杯になったもんさ。
昔はどの家にも竈(くど)がありましたやろ。それが熾火(おきび)になりますやろ、そこで炒りますんや。あとは七輪へ火を入れてやりましたんさ。
あられ炒りで炒るとふわーっと膨らむんさ。
※著者注:竈(くど)とはかまどのこと。昔の家屋は土間(どま)にかまどが置かれ、調理や暖をとったりした。京都では「お竈(くど)さん」と言うが、私の出身地の大阪では、祖母が「へっついさん」と言っていた記憶がある。
昔はどの家にも竈(くど)がありましたやろ。それが熾火(おきび)になりますやろ、そこで炒りますんや。あとは七輪へ火を入れてやりましたんさ。
あられ炒りで炒るとふわーっと膨らむんさ。
※著者注:竈(くど)とはかまどのこと。昔の家屋は土間(どま)にかまどが置かれ、調理や暖をとったりした。京都では「お竈(くど)さん」と言うが、私の出身地の大阪では、祖母が「へっついさん」と言っていた記憶がある。
竹本
なるほど、食後に熾(おき)で作るのは理にかなってますね。
ちかさん
天ぷら鍋で揚げてみるより、ゆるーい火で炒ったほうが旨いわな。
竹本
食べ方というか味付けはどのように?
ちかさん
塩を振ってみたり、砂糖醤油と絡めてみたり。あと美味しいんは、砂糖を煮といて糸引くくらいな、それを絡めてやるのも旨いでな。
竹本
砂糖で飴(あめ)を作るってことですね。
ちかさん
そうやそうや、うっかりしてると焦げるやつね。サッと絡めるんよ。
竹本
腹持ちのいいもち米と、すぐエネルギーになる糖分と絡めるなんて、上手いこと考えてありますね。
ちかさん
そうやなぁ。昔は田んぼの合間に食べましたな。昔は何俵と作りましたな。山のように。
昔は甘いもんが少なかったから貴重やったん。
昔は甘いもんが少なかったから貴重やったん。
利通さん
昔は、兄弟が多かったやろ。それで竈(くど)があって、熾火(おきび)があって、子どもらの腹持ちがエエもんがよかったんと違いますか?
ちかさん
あと、お茶を掛けても美味しいな。お茶漬けのあられやね。
利通さん
お餅の味がして美味しいで。ほんまに餅しか入ってへんからな。
昔は粟とかキビとか入れてちょっとでも多く作ろうってことでやりましたな。
昔は粟とかキビとか入れてちょっとでも多く作ろうってことでやりましたな。
竹本
こういう日本ならではの食文化を残していきたいものですね。
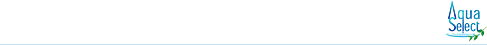
竹本大輔